イースター/復活祭とは
日本でも春のイベントとして浸透してきたイースター。イースターとは「復活祭」の意味があり、十字架にかけられて処刑されたキリストが3日後に復活したことを祝うキリスト教の祭日です。キリスト教では「クリスマスと並ぶ」「それ以上」ともいわれるとても重要なイベントで、生命の復活と繁栄を祝う春のお祭りです。
キリストの12人の弟子の一人・ユダが裏切り、反逆者として十字架にかけられたキリスト。その処刑から3日後の日曜日の早朝、聖母マリアたちがキリストの墓を訪れると墓はもぬけの殻で、キリストの復活が告げられた…という記述が聖書にあります。このキリストの復活に弟子たちは大喜びし、最大の奇跡としてお祝いをしたことが今日のイースターの起源です。
ちなみに現在の暦で日曜日が休日なのは、このキリストの復活に由来します。
関連記事はこちら 曜日(七曜)って何?なぜ1週間は7日で、日曜日が休日なのか「イースター(Easter)」の名前は、古代ゲルマン神話に登場する春の女神「Eostre(エオストレ)」に由来するとされていて、イースターにはキリストの復活だけでなく、春の訪れを祝う意味もあります。
12月25日のクリスマスはキリストの降誕祭ではありますが、新約聖書ではキリストの生まれた日がはっきり書かれていません。そのためクリスマスは「キリストの誕生日をお祝いする日」ではなく「キリストが生まれてきた事実をお祝いする日」というのが正しい解釈です。
一方、イースターはキリストが起こした奇跡の中でも「自分自身(キリスト)の復活」という衝撃的で感動的な奇跡をお祝いする日ですから、キリスト教ではクリスマスよりもイースターの方が重要視されているという見方もあります。
モアイ像で有名な「イースター島」は、イースターの日(1722年4月5日)に発見されたことから名づけられたそうです。

イースターの日付
イースターは毎年決まった日ではありません。春分の日の後の、最初の満月の次の日曜日と決められています。この定義は西暦325年に行われたキリスト教の会議「第1ニカイア会議」で決められました。
キリスト教は大きく分けて西方教会と東方教会があり、教派によって使用する暦が異なるため、イースターの日も変わります。
- 西方教会
-
- 現在日本でも使用されているグレゴリオ暦を使用
- 復活祭:毎年3月22日~4月25日のどこかの日曜日
- 東方教会
-
- 一部を除いて、ユリウス暦を使用
- 復活祭:毎年4月4日~5月8日のどこかの日曜日
| 西方教会 | 東方教会 | |
|---|---|---|
| 2025年 | 4月20日 | 4月20日 |
| 2026年 | 4月5日 | 4月12日 |
| 2027年 | 3月28日 | 5月2日 |
イースターのシンボル
イースターエッグ

イースターで欠かせないのがカラフルにペイントされた「イースターエッグ」です。卵は新しい生命の誕生を意味する復活の象徴であり、一度処刑され復活したイエス・キリストを連想するアイテムです。
イースターエッグの起源にはいくつかの説があり、1つは「イエス・キリストの復活は赤い卵と同じくらいありえない」と言ったある皇帝の言葉を由来とする説や、イースターの前の四旬節(後述)の断食で卵を食べることを禁じられていたから、とする説などがあります。
カラフルにペイントするようになったきっかけは、生卵とゆで卵を区別するためだったという説も!?

イースターバニー

もうひとつイースターで欠かせないのが「イースターバニー」です。うさぎは一年に何度も妊娠と出産を繰り返すことができ、さらに一度にたくさんの子供を産むことから、キリスト教では生命力や繁栄の象徴とされています。
しかし古くからイースターに関わってきたわけではなく、イースターバニーが生まれたのは16世紀頃のドイツと考えられていて、その後世界へと広まっていったようです。また、イースターバニーは西方教会のイースターのシンボルで、東方教会にはイースターバニーの習慣がありません。
イースターバニーの起源には諸説あり、正確なことはわかっていません。一説では、イースターの名前の語源となった春の女神エオストレが野うさぎを従えていたから、と言われています。
現代のイースターではイースターバニーは子供たちにイースターエッグを運んできてくれる存在です。イースター前日の夜に玄関の前にバスケットを置いておくと、イースターバニーがイースターエッグと一緒におもちゃやお菓子を入れておいてくれたり、エッグハント(後述)ではイースターエッグを隠したりと、まるでサンタクロースのような役割を担ってくれています。
イースターの風習
食事(パーティー)

クリスマスと同じくらいのめでたい日ですから、イースターの日は家族や友人とパーティーを開き、ごちそうを食べるのが定番です。これと決められたメニューはありませんが、イースターのモチーフである卵を使った料理を用意することが多いです。
ゲーム
イースターのシンボルである卵を使ったゲームで遊びます。

- エッグハント
- 家の庭や公園に隠したイースターエッグを家族や友人と探すゲームです。子供には「隠したのはイースターバニーだよ」と伝えましょう。
- エッグ&スプーンレース
- スプーンに卵をのせて運ぶ競争です。大人はスプーン、子供はお玉などのハンデを付けても面白いです。生卵よりもゆで卵、おもちゃの卵を使った方が割れる心配はありません。
- エッグローリング(卵転がし)
- 卵(ゆで卵やイースターエッグなど)を割らないように転がしてゴールの速さを競うゲームです。坂の上から転がしたり、傾斜が無ければスプーンなどで転がします。卵は楕円形なのでまっすぐ転がってくれないので意外と難しいゲームです。一説では、キリストが復活する際に岩を転がしてどかせたという伝承が由来と言われています。
パレード
アメリカ・ニューヨークのイースターといえば、イースターパレードです。このパレードに欠かせないアイテムが華やかに飾られた帽子「イースター・ボンネット」で、集まった人たちは思い思いに作成したイースター・ボンネットをかぶってパレードに参加します。昔は生花や造花、リボン、貝、羽などで飾り付けていましたが、最近ではイースターエッグやウサギの耳など奇抜で遊び心のある帽子も増えてきました。
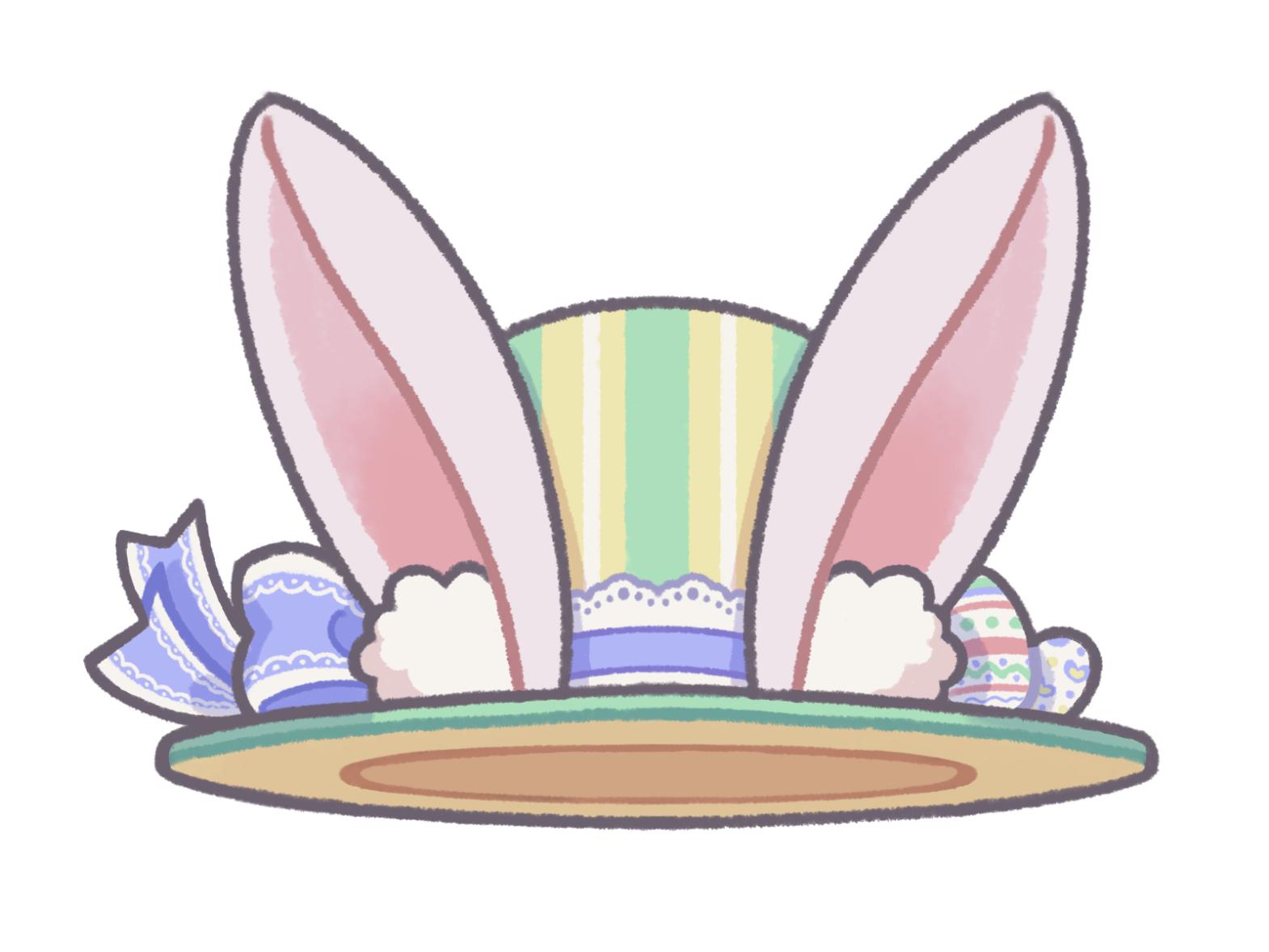
イースターの準備期間「四旬節」とは
イースターの46日前(灰の水曜日)からイースターの前日(聖土曜日)までを「四旬節(しじゅんせつ)」といい、この期間は伝統的に食事の節制(断食)やお祝いごとの自粛が行われてきました。
四旬節とは「40日間」の意味があり、40の数字はキリストが荒野で40日間断食したことに由来しています。主日(日曜日)には断食しない習慣だったため、復活祭の46日前から四旬節が始まります。
この期間は古くは肉・卵・乳製品を食べることを禁じ、一日に一度しか十分な食事を摂ることができない厳格な節制が行われました。現在では教派によって違いがありますが、
- 好きな食べ物を食べることを控える
- 好きな娯楽を自粛する
- 節制の代わりに慈善活動を行う
など、形式的なものに変わっているようです。
「復活前のキリストの受難と死は、私たち人間の罪をつぐなうためだった」という考えから、キリストの苦しみを追体験して分かち合おうというのが四旬節の意義です。
四旬節の直前には「カーニバル(謝肉祭)」というお祭りが行われます。古代~中世の信者は四旬節の間に肉を食べられずお祝い事も禁止されていたため、その前にごちそうを食べて大いに騒いで盛り上がっていました。
四旬節が形式的なものに変わった現在でも、この時期に仮面をつけて仮装行列を行うなど、羽目を外して大騒ぎするお祭りの習慣は世界各地に残っています。
